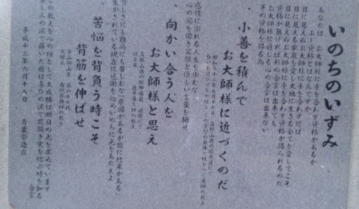一隅を照らしたい凡人の札所巡り
四国88札所 区切り1回目詳細
| 1〜21番札所 |
|---|
2012年10月3日夜〜2012年10月8日早朝 |
|
斜め前の席に杖笠持参の女性が座ったので発車までの間、いろいろと尋ねる。 完全歩き遍路で今回は17番札所井戸寺スタートのこと。 JR徳島駅前には定刻より6分早く到着したため、予定より一つ前のJRに乗車可能となり 飛び乗り 即発車。 板東駅には一つ前の駅から乗車してきた同年輩の男性と二人だけが下車。 訊くと霊山寺に向かうとの事で同行を願う。聞けば足立区在で高速道路のバス停を一つ間違え手前で降車したため電車で来たとのことで今回が2巡目の開始とのこと。 1番札所霊山寺 彼は遍路用品一式を1番札所前左側の店で前回と同様に購入すると述べたが自分は境内に入り、本堂右隣の売店にて杖、笠、納経長を購入し備え付けのサインペンで名前を記入し、持参の白衣に着替え、本堂にて参拝。 (売店の店員が杖を本堂前に置き忘れて出発する人が最近多いと注意してくれた) 納経帳には既に一番札所の朱印が押されており、 番外札所の印は別途朱印帳を用意するとのこと。 読誦後 境内を巡ることなく 即出発。門前の土産物屋前のベンチにて先刻の男性が身支度をしていたので 会釈して歩行開始。国道沿いの歩道を歩く。 300mほど前方に男性遍路さんが自分とほぼ同一の速度で歩んでいる。平日の朝7時半で国道はひっきりなしに乗用車、トラックが通り、運転手は一様に自分を見ているように見える。 |
|
| 道標に導かれ国道を右折して正面に2番札所を認める。 | |
読誦後、御朱印を頂き、門前の地図にて遍路道を(墓地内を通る)を確認して歩き出すが異様な雰囲気であり、引き返し先ほどの国道まで戻り、国道沿いに少し遠回りではあるが歩行開始。 途中で女性の遍路さんに追いつく。 韓国の方で漢字は判読可能だが日本語会話は困難とのことで以後つたない英語力を駆使しながら同行。 途中民家の主婦から手作り小銭いれの接待を受ける。 2番札所極楽寺 道筋の民家の形状や果実畑等を説明しながら歩き、途中の道標を見落とし、5分ほど戻り3番札所金泉寺に着く。寺には先ほど2番札所では見かけない私服の参拝者。多分乗用車にて追いついた方々であろう。 |
|
韓国の婦人と会話しながらの道中となったため、ずた袋内の地図の確認が疎かになり、道標や通りがかりの車の運転手に尋ねながら歩く。 後日マップで確認すると歩行用ではなく車両用の道を辿った様である。 途中車遍路の方からお茶ペットの接待を受ける。 高速道路下を過ぎてから家並は途絶えなだらかな坂を上る。絶好のピクニックコース。 4番札所大日寺 読誦後 五百羅漢前まで戻り、そのまま5番札所地蔵寺に向かう。地蔵寺横の駐車場内に駐車中の車の中で弁当を食べているお遍路さんがいる。(大日寺への往復路にてほかの徒歩遍路さんとはすれ違わず) 地蔵寺にて御朱印をいただく際に付近に昼食を供す店があるか否かを尋ね、県道を右折して直ぐ右側にあることを告げられ、昼過ぎの満席の定食屋で相席にて食事を取る。 遍路さんに対しては接待で一律50円引きといわれ感謝。 県道は交通量が多く路側を一列で歩かざるを得ないが一歩横の遍路道に入ると偶にライトバンが通る程度。 行き違う小中学生の殆どが我々に挨拶の声を掛けてくれる。学校の指導か家庭での躾か?いずれにせよこちらも元気に挨拶を返す。 彼女は道端の槿の木を指差し、韓国の国花と言い、此の辺りに植栽されているのをしきりに感心している。 6番札所安楽寺にて読誦し、御朱印を頂いた後宿坊の予約をしてあることを伝え境内本堂と棟続きの宿坊に行く。受付の人は韓国の婦人に英語で要点を尋ね 予め英文で印字したメモを提供。 午後5時より本堂内内陣にて読経と法話による法要。参加者は自動車巡礼の夫人4人組と歩き遍路の男性が二人。それに韓国の婦人と私の計8名。正味一時間半 終了後、食堂にて8名が自己紹介などをしながら食事中に今朝会った足立区の男性が食堂に到着。 先刻宿坊に到着したが体調が優れずそのまま部屋で休息していたとの事。 男性三人はいずれも明日は11番札所藤井寺傍の民宿に泊まり、焼山寺に登るとのことで情報交換後各自個室に戻る。男性二人はこれから洗濯する由  6番札所安楽寺宿坊の夕食 |
|
| 2日目 6時半からの朝食を取り、宿坊出発。何人かは本堂にて再度読誦後に出発とのこと。 境内には既に外部からの参詣者が参内。 7番札所十楽寺に到着すると既に先刻の自家用車の婦人4人組が納経所にて受付中。 他にも安楽寺宿坊に泊まらなかった遍路さんが数組境内に所在。 境内には愛染明王を祭る楼がある。 夫婦等カップルは時間を割いて潜るであろうが先を急ぎ読誦を終え、朱印を頂き出発時に安楽寺にて朝の読誦を終えた宿泊者達が到着。 |
韓国の婦人は元、小学校の教諭であると述べ、道々 小学校や保育園の校舎の写真を撮っている。 次の札所の後、徳島駅に戻り、松山国際空港からソウルに帰国するとのこと。 8番札所熊谷寺にて読誦時に昨夜宿坊に同宿した今回2巡目という70代の紳士が追付いて来た。 彼女がここから徳島駅に戻るため最寄のJR駅までタクシーで帰る予定と告げると この辺のタクシーは呼んでも直ぐ来ないので御朱印受領の前に電話をしておかないと時間をロスすると助言。 8番札所熊谷寺にて韓国婦人と
礼を言い。納経所前の看板記載の番号に電話し、タクシーを呼び寄せ到着まで彼女と一緒に待機することとし、彼女にその旨を伝えた。 老紳士の言うとおり,約15分後に到着したタクシーに婦人が日本語が不自由なことと行き先が鴨島駅であることを伝えた。 婦人は前日の昼食での私の接待のお返しとして納経所にて購入した納め札入れを差し出し。いつかソウルに来ることを待つと述べ駅に向かった。 熊谷寺にて時間を費やした為 急ぎ田畑の中、用水路のほとりを、途中一人歩き遍路の男性を会釈して追越して9番札所法輪寺に向かう。 |
|
| 法輪寺の塀脇に遍路姿の男性が経文を唱え托鉢を行って居た。 境内には昨日今日見かけぬ遍路さん方が何人もいる。 殆ど全てが車で私を追い抜いてきた方々と思う。 |
途中 逆遍路を目指す私と同年輩の歩き遍路男性と擦違い、挨拶を交わす。 9番札所法輪寺 お遍路の道標に従い畑の中に散在する民家の横を右折左折しながら進む。 しかし百メートルほど隔てて片側1車線らしき車道が通っているらしいことが歩きながらも確認できる。 不審に思いながらも律儀に概略数十メートル毎に表示される道標に従い幅数メートルの小径を辿る。 (保存協会発行の地図を後日確認すると確かにこの区間はほぼ直線の新道を辿るようにとの赤線が記入されてはいた。) 灌漑用溜池の縁を大回りし、岡の中腹に細々と続く自転車も通れぬ小径を辿り、やっと かの新道と合流する。 |
|
| 合流後、一気に右折し北側の丘陵地帯に入り両側に民宿や土産屋等かっては繁盛したであろう商家の並ぶ細い急峻な坂道を登り10番札所切幡寺の山門を潜る。 |
先刻8番札所にて韓国婦人にタクシーを手配中、会釈して追い抜いていった大学生二人ずれに石段途中で擦違う。 尋ねると今日は藤井寺から焼山寺に向かい途中のどこかの庵にて仮泊とのこと。 若さを讃え、激励し合って分かれる。 本堂にて読誦し、石段を下る途中先程の70代紳士と擦違う。 10番札所切幡寺 石段を降りきったときは、八大様に参拝することを忘れ平地に戻り 只管 田園地帯を南下し、市街地に入る。 |
|
| 振り向けば木々に覆われた山の中腹に切幡寺の屋根が一つ確認できる。 |
御好意に甘え店内の椅子に腰を下ろし、お茶を頂きながら女主人の話を聞く。 数年前に有名女優のテレビ探訪番組の一行が来店し、全員に清涼飲料水と軽食を振舞ったのにマネージャーが出したお礼の金額が少なく赤字になった。 その後其の女優は一度も店に電話をよこさないなど、なんとも現実的な話をする。 吉野川支流の前、市街地の途切れる処に遍路小屋を認め、一時休息する。 田圃から切幡寺を仰ぎ見る
車両が途中擦違うことが不可能な潜水橋を渡り、農家が視界に無い畑一面の高台に出る。 軽四輪を傍らに止めて小休止している男性は これから落花生を取り出すところだと云う。隣の畝に並ぶ葉の大きな植物は里芋と答えてくれた。 |
|
 10番札所11番札所間沈下橋 (潜水橋) 二つ目の潜水橋(吉野川本流)をわたり、土手を登ると完全な市街住宅地。 道標の無い三叉路等では道を尋ねながら黙々と歩く。 途中足裏に肉刺が出来た様に感じ、路肩の石垣に腰を下ろし、二枚履いていた靴下を左右及び内外を交代させて履き直す等、30分ほどの休憩を取って再出発。 かなりペースダウンして11番札所藤井寺入口道標に辿りつく。 |
不安を覚える頃やっと 『 藤井寺 』の道標を認める 左の竹薮越しに眼下に家並が見える。 小路を下り寺の駐車場管理小屋の裏口に辿りつく。 山門前には観光バスや車で来た参詣人が多数。 駐車場管理人に 「 切幡寺から歩いて来たが この小路で良かったのか?」 と聞くと 「 この車道が出来てからは殆どこの(車)道から来る 」 とのこと。 鴨島駅に向かうならこちらが近道との言葉を受けて藤井寺参拝。 11番札所藤井寺 読誦後 駐車場管理人が小屋に居ないため そのまま川沿いに車道を暫く歩くと三叉路に出る。 左折すれば先程の分岐点に達すると思い、右折して暫く歩き、付近の民家の人に駅への道順を尋ねると、実は駐車場門前から川沿いではない右側の道を行くべきであったと告げられる。 其の場所からの駅へのルート(約30分弱)を親切に教わる。 30分程度ならと気楽に歩き出したが吉野川支流の橋を渡るあたりから又足が痛み始め、明らかにペースダウンし、県道を越えた後の駅までの商店街は電車の予定発車時刻に間に合うよう懸命に歩く。 駅自動販売機で適当な区間の切符を買って陸橋を渡りホームに着いたのは、電車の到着1分弱前。 徳島駅にて切符精算をし、徒歩7分のアバンテイホテルに着く。 シャワーを浴び一休みしてからフロントで聞いた薬局に絆創膏を6時の閉店間際に買求め、駅前に戻り、そごうデパート地下の簡易食堂にて夕食を取る。 前夜同宿の婦人4人組からの情報で足の指に絆創膏を巻きつけ、足の裏には持参した湿布を貼り、靴下だけを洗って即寝る。 3日目 6時10分徳島発のJR乗車予定だったが早く目覚めたため早めにホテルを出る。 昨日の足の痛みは引いていたが大事をとり、リュックをコインロッカーに預ける事とし、駅員に尋ねると駅舎内は7時開業だが外にも在ると教えられ急ぎ確認収納し、駆け足で駅に戻り昨日と同じホームからの発車寸前の電車に飛び込む。 府中(フチュウ と読んだら コウ と読むと2度ほど訂正を受けた )駅で降りたのは自分の他は大垣から来たという男女1組のみ。 自分と同年輩の彼等は 昨夜名古屋駅を発深夜バスで発ち、今朝一番電車を徳島駅構内で待って乗車したとのこと。 数年前から区切り遍路を続けており、足腰の達者な元気な間にと 先ず急峻な区間を踏破して、最後に残った今回の平坦な土地に連なる13〜17番札所を打てば結願するとのこと。さまざまな廻り方があるものだと思う。 |
|
| 無人駅の府中駅駅舎内に17番札所井戸寺までのルートを示す地図が無く、程なく現れた 徳島方面上り電車に乗る予定の勤め人に概略道順を聞いて彼等と前後して出発。 |
本堂と大師堂前にて読誦し、寺名の由来である井戸を見て、瓶詰めの販売用の水の陳列を見ながら午前7時の御朱印受付開始を待つ。 17番札所井戸寺境内 御朱印受領後、元来た道を引き返し、線路を越えて両側に民家の切れ目の無い市街地の国道沿いを歩く。 此処から13番札所までは通常とは逆向きに歩くことになり、道標が整備されているか否か心配であったが国道には16番札所入口の表示があった。 国道を左折し南下する道の傍らには用水が平行して走り、中には体長10cm程度の小魚が無数流れに向かい餌を求めているのが認められる。 |
|
| 暫くすると先行していた 大垣の男女1組がどうも通り過ぎたらしいと戻って来た。 |
何のことは無く、四つ角十字路ごとに必ず左方向を確認して歩けば容易に確認できる場所に16番札所観音寺はあった。 境内は先刻の井戸寺以上の賑わいであった。 周囲を民家に囲まれた市街地ということもあり、敷地はかなり狭い。 16番札所観音寺 読誦、納経受付を終えた頃に、井口寺で読誦していたお遍路さん方が到着し、読経を始めた。彼らも車両を用いずに歩いて来た遍路であろう。 |
|
| |
くと家並みが途絶え田畑が始まるが遥か前方に大きな寺院の 屋根が見える。 多分あそこがそうであろうと見当をつけて歩く。 田畑地から又、住宅地に入った直後 通常の歩き遍路と擦違 う、挨拶しながら国分寺までの距離を尋ねると直其処という。 結局北側から南進するルートを取る逆遍路は正門が南面す るお寺の敷地沿いに迂回し、境内の縁を廻り、迂回して到着。 (北上する正常ルートであれば、容易に山門に到達し、読誦後 は外部から見つけ難い通用門から観音寺へ抜けられた.) 15番札所国分寺山門 |
|
|
|
国分寺脇の駐車場から出てきた団体ツアーお遍路とすれちがう。 殆どが私より年上の女性のように見受けられる。団体ツアーは賑やかにかつ華やかに見える。 14番札所常楽寺との間隔が徒歩10分で平坦なこともあり、バス団体遍路もこの区間は歩くらしく周囲の雰囲気も何となく華やぐ風情。 常楽寺は境内全体が大きな一つの岩の上に在る様な感じを抱かせる地面にある。 15番札所国分寺本堂 此処にも団体遍路が2団体既に居り、御朱印を頂く間に別の団体が到着。いずれも本日13番札所からはじめた正常ルートの参拝団であろう。 |
|
札所の前の地図を参考に大日寺を目指すが即 T字路や三叉路に出くわし、其のつど民家の住人や庭職人に聞いて歩む。 地元の人にとって当たり前のルートでも、始めて、しかも逆ルートを歩む遍路にとっては農村部よりも入り組んだ市街地の方が迷い易い。 一宮橋を渡りきらずに途中階段を右折して遥かかなたの大日寺と思われる大屋根を目指して歩む。 14番札所常楽寺境内 |
|
| 途中私と同年輩の正常ルート歩き遍路と擦違い、コスモスの咲く畑を横目に地図どおり13番札所大日寺に到着。 大日寺の前は国道を隔てて阿波一宮。 此処にも数団体のお遍路ツアーがほぼ同時に到着し、混雑を避けるために本堂と大師堂の参詣順を逆にして凌いでいた。 |
社務所売店にて購入しようとしたが納経所と離れた位置で係 員が居ないため断念。 大師堂の軒の立派な木彫飾りを鑑賞後、御朱印を頂く際、 付近で昼食を取る場所を訊く。 この辺の旅館民宿は全て予約制でだめだが直ぐ其処のロ ーソンには弁当があるはずで、其の前がバス停だからバスを 利用するのならば丁度よいであろうとの事。 この札所の前がバス停なのでそんな近距離にバス停があ るのかと、気安く歩き始めた。 13番札所大日寺 直ぐ其処と云われたローソンまで結局10分歩き、バス発車時刻を確認してローソン内にて弁 当を物色してレジに並ぶ。 私の前には本日、井口寺、観音寺、大日寺で私の出発時に朗々と経を唱えていた男性遍路が たまたま並び おでんを注文していた。 私もそそられて別途おでんを2種注文し、コンビニの店前のベンチにて二人で一緒に昼食をとる ことになった。 彼は四国歩き遍路通算21回目と云い。今回は逆遍路でこれから歩いて12番札所焼山寺まで登 るとのこと。 時間的に焼山寺に今日中に上るのは難しいのではというと、登れるところまで行って其処で野 宿するとの事。 A3版の自分で調べ作成した野宿遍路指南コピーを譲って頂く。 素足スニーカーのいでたちであり、出身は小松島市。88札所のいろいろな事情に精通してお り、いくつかのお寺さんの裏面を語ってくれた。 名前は真理魚 哲 と名乗った。 歩いて焼山寺に向かうという彼をコンビニ前に残し、2分遅れの寄居中行き徳島バスに乗る。乗 客は私の他は老婦人一人。 |
|
| 蛇行する川に沿って走るバスの車窓からの対岸の木々の緑は飯能から秩父に向かう電車の 窓からのそれより、至近距離の所為か、 川の水量の豊かな所為か 吾身に迫る。 終点の寄居中バス停は大井川鉄道の二俣川宿を思い出される鄙びた町並み(秩父小鹿野役 場前界隈のほうが遥かに殷賑) 徳島バスが誰も乗せずに直ぐUターンして走り去った後、小型バスが2分遅れで停車し 「 焼山 寺の麓まで」 と念を押して、自分一人を乗せて走行。 |
先程のバスの運行間隔は2時間ほどあるので多分13番札所から逆ルートにて登ってきたと推測。 終点で運転手さんの「お寺から又戻ってくるのなら4時31分が最終だから。今まで殆どの人は時間までに戻ってきている」との助言に礼を云い歩き出す。 12番札所焼山寺杖杉庵 直ぐ前方より同年輩の婦人が三々五々坂道を降りてきたので「お寺さんまでどのくらいですか?」と声をかけると「私たちはバスを使ったから」とのこと。 登山の傾斜角は坂東の八溝山、都幾山と粗同じ。 途中から車道と別れ遍路道を登る。 35分ほど登った時に始めて下山者と擦違う。軽快な足取りの若い女性で、お寺までの距離を訊くと降り始めて15分とのこと。 下りで15分なら上りで30分程であろうと元気が出、まもなく杖杉庵に到達。 暫く車道を歩き再び急峻な遍路道に入ると夫婦ずれの遍路者に遭い、「まだまだありますよ」と云われ、おやおやと思いながら登って昨日熊谷寺にて助言を受けた老紳士とまたもや再会する。 どうですか?との問いに対して「民宿を出てお寺まで7時間掛かった。ここからはまだまだ1時間ほど続くよ」と云われ一時戦意喪失。 気力を振り絞り登山開始、まもなく上のほうから賑やかな話し声が聞こえ始め、再び車道に出て12番札所焼山寺到着。 |
|||
|
近在の方が早朝の参拝に訪れる中、納経所の入口が開き、御朱印を恐る恐る願い出ると 『本当は7時からですよ 』 と応じてくれた。 礼を云い、他の遍路者が到着する中を予定より早く出発。 駐車場を出て直ぐ牧舎横の小路に入る。 義経の峠越えの看板のある竹薮の中は迷路のようである。 18番札所恩山寺境内 道標に従い里に出た後は畦道を辿り農家の軒先を通る獣道(私道?)を右折左折して先刻主人に言われた場所で県道に出る。 当初の予定とおり立江寺から恩山寺に向かって逆打ちしていたら 絶対に見逃すルートと後日思い返して改めて民宿鯉の里の主人に感謝する。 県道を道標に従い立江寺を目指すと前方から来た車が停車し私に 『 鶴林寺に行く道を知らないか?立江寺から ナビ に従って走っているが同じ所に戻ってしまう 』 と訊く。 『自分は恩山寺から来たが、其の先の県道を左折すれば麓に行くバスの走る道がある筈 』 と応じる。 立江寺に纏わる逸話をふと思い出す。 まもなく鮒の里の前を通過し立江川を渡る橋の上で地元中学生の一団の元気な挨拶にこちらも元気良く応じて街中に建つ19番札所立江寺に到着。 |
|
| 境内には数組の遍路者がおり、鐘を撞いた後有料の蝋燭を無人抽斗で求めて線香を供え読誦。 元々この寺の宿坊には前日到着時間を早めに設定出来れば泊まる予定を立てていた所。 |
男性30代一人遍路者と前後して寺を出、立江橋を再び渡り、T字路に戻る。 傍らの道標に右恩山寺、左鶴林寺とあるが乗用車からは判読不可能な歩き遍路者用の道標。 19番札所立江寺 右折して宿に向かう。彼は左折して鶴林寺へと向かった。 民宿の庭先から改めて宿全体を見る。昨夜は感じなかったが意外と小さな家、多分隣の家屋 も使用しているのではと思う。 リュックを車に運び、鶴林寺に向かう。恩山寺経由ではなく、先程のT字路経由で、まもなく先程の男性遍路者を追越し、暫く走って恩山寺方面からの道と合流して道幅が広くなり宿の主人が 『 昨夜の宿泊者 』 という西洋人等を何回か追越して生名バス停前で下車。 |
|
付近の販売機で清涼飲料水を買求め、バス停の時刻表での一番始発バス到着より凡そ1時間半早い到着であることを確かめ、リュックの緩みを再点検し9時前に登山開始。 民宿 『 鯉の里 』 最初は周囲は畑や潅木のため振り返ると川向こうの南側斜面の山肌が陽に映えて気持ちよく足取りも軽やかであったがやがて樹林地帯に入る辺りから傾斜が急となり、スピードが落ち、いつの間にか気づかぬうちに一人の軽装登山者に追付かれた。 顔を見ると昨夜同宿の同年輩の遍路さんで彼は歩幅を小さく極力凸地を避け平地に足を下ろすようにすれば疲労が少ないと忠告し先行した。 |
|
| その後 やはり民宿の主が 『 今朝早く出立した 』 と車中から指し示した軽装の西洋人二人に抜かれ 広島在のオフイスレデイに抜かれた。 |
そして登山開始後1時間45分後に20番札所鶴林寺に到着 蝋燭、線香ともに使い切っている為 夫々、本堂太子堂にて買求めて点灯、点火して供え読誦する。 鶴林寺への登山途上の風景 境内は車で登ってきた団体や個人で賑わい、先行したO.Lには再会したが他の男性陣は既に出立したとみえ、確認できなかった。 |
|
| 納経所にて御朱印を頂く際、係員は一目で車で来たのか徒歩で登って来たのかが判るらしく、車で来たと思われる人には御朱印代のほかに駐車場代を請求し、徒歩で来たと思われる人には 次の札所に向かう道を指し示すには感心する。 昼食を取る適切な場所が混雑のため見当たらず、小休止して下山開始。 |
何人かに追い抜かれた後、民宿が用意してくれた握り飯を倒木に座って食す。 足の裏を確認している約30分の小休止の間に先程の O.L に会釈されながら抜かれ、下山再開。 一度車道に出た処で太龍寺ロープウエイの道標と歩き遍路道の両方の表示があり、一瞬戸惑ったが遍路道を選択する。 痛みへの対応の抜本策として、長いコンクリート製石段の処で腰を下ろし、両足の裏に湿布を張り直し、足の指の間にバンドエイドを張り直し、靴下も左右交換裏表逆にして3枚重ねて履き靴の紐を締めなおす。 20番札所鶴林寺境内 再度30分弱の時間ロス(其の間に50代男性一人が会釈して先行)後 歩行再開。 暫くして里に出、無料休憩所にて誰も休息していないのを確認し、水井橋の手前の自販機でボトルを新たに入手して、比較的楽な舗装された単調な坂道をリズムをつけて太龍寺に向けて新たに登山開始。 |
|
| 単調な坂道を無心にリズムをつけて機械的に歩む程に先行していた50代の男性及び30前後の男性に追付き、 その後はお互いに小休止の間に抜いたり抜かれたりを繰り返しながら進む。 |
境内にて昨夜民宿にて会話した台湾から来た青年と今日始めて再会した。 彼はロープウエイを用いずこれから坂口屋まで下ると言う。激励して本堂に向かう。 21番札所太龍寺山門 本堂は再建中であり、仮本堂の前にて読誦中、ロープウエイを用いての団体参拝団が到着。 |
|
| 先達が私の読誦が終わるの待っていることが気配で感じられ、早口にて般若心経にて読経を切り上げる。 太子堂の社の欄間彫刻は立派。 朱印所の右隣の窓越しに覗く天井の龍の絵も立派。 |
ロープウエイの下りのみを利用する人は稀のようで、切符売り窓口は改札口前の売店が兼務。 ロープウエイからの眺めは箱根大涌谷のそれと比肩できる。途中の乗継が無い為、全長ではこちらが勝る。行程約10分。 太龍寺境内の石碑文言 途中進行方向左粗水平位置に数頭の狼の像が設置されている。 |
|
| ロープウエイの乗客20余名は降車後全て駐車場に向かう。 付近にバス停が見当たらない為 駐車場横のホテル(会館?)に入り、和食バス停の所在を尋ねる。 |
前日に確認していたバス便より一つ早めの (1時間早い)徳島駅行きのバスに乗車。 今朝生名バス停を予定より1時間半 早めに出発できたのに 和食バス停発車時刻において予定より1時間の早めと差を詰められた。 太龍寺ロープウエイ山頂駅からの景観 結局 歩行行程は予定より30分余計に費やしたことになる。 バス停桑野上での降車時、運転手にJR桑野駅までの道順を訊き、人通り皆無の道を数分歩き、無人駅に到着。 駅の時刻表を見ると徳島行き普通上りは1時間半程待たねばならず、特急は後数分で到着することが判り、逡巡の後、販売機で特急券をも買求め上り線ホームにて待つ。 2両編成特急の車掌に阿南駅に停車することを確認して乗車、車掌は阿南は次の駅と応える。 阿南駅広域トイレにて着替え、駅から徒歩10分の大型郊外型ショッピングセンタービル内で徳島ラーメンを食べて休憩。 駅前バス発着所からはJRバスより1時間早く徳島バスが東京渋谷まで発車させていることが判り、徳島バスの運転手もJRをキャンセルして乗車するように勧めたが予定とおりJRバスにて(徳島駅までの乗員は自分一人)新宿に向かう。 |
|
| 帰宅後 次回用の適切な靴を買い求む。 |
| |
| 区切り2回目詳細 |